文・石鍋健太
谷崎潤一郎のメモリアルイヤーにちなんだブログの第2弾です。
前回のブログ「何も捉える気がないのに凝視―谷崎潤一郎の言葉と眼差し その1」はこちらからどうぞ。
■ 陰翳 = オブジェ
谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」(昭8・12、9・1「経済往来」)は同時代評や先行研究において、多くの場合、現代では失われてしまった「陰翳」をあらためて日本独自の伝統美として掲揚した作品、あるいは谷崎自身のかつての「西洋礼賛」の反動として読まれている。※1 確かに谷崎は「陰翳礼讃」において、至上の位置に据えられた「陰翳」美を大前提とし、その実例と感想とを列挙するという趣向を採用している。が、今日のところはいったん、伝統美としての「陰翳」という見方をすっかり忘れよう。その上で、「陰翳礼讃」に提示されている「陰翳」とはいかなるものなのか、いかに書かれているのか、ということに目を向けてみたい。
たとえば日本家屋独特の「陰翳」を伴って変化する食事体験について、谷崎は次のように書く。
私は、吸い物椀を前にして、椀が微かに耳の奥へ沁むようにジイと鳴っている、あの遠い虫の音のようなおとを聴きつつこれから食べる物の味わいに思いをひそめる時、いつも自分が三昧境に惹き入れられるのを覚える。(中略)日本の料理は食うものでなくて見るものだと云われるが、こう云う場合、私は見るものである以上に瞑想するものであると云おう。
もう一つ、「羊羹」の例も。
玉のように半透明に曇った肌が、奥の方まで日の光りを吸い取って夢みる如きほの明るさを啣んでいる感じ、あの色あいの深さ、複雑さは、西洋の菓子には絶対に見られない。(中略)あれを塗り物の菓子器に入れて、肌の色が辛うじて見分けられる暗がりへ沈めると、ひとしお瞑想的になる。人はあの冷たく滑らかなものを口中にふくむ時、あたかも室内の暗黒が一箇の甘い塊になって舌の先で融けるのを感じ、ほんとうはそう旨くない羊羹でも、味に異様な深みが添わるように思う。
ここに書かれているものは、「鮫人」(前回のブログ参照)においてそうであったように、実際の食物や食事体験とはあまり関係がないように思える。「陰翳」を伴った「羊羹」は、食物としての役割を剥奪されるどころか、非常に抽象的な何か別の存在へと変貌させられている。そして、この抽象化作業の原動力となっているのは、谷崎の次のような「空想」である。
もし東洋に西洋とは全然別箇の、独自の化学文明が発達していたならば、どんなにわれわれの社会の有様が今日とは違ったものになっていたであろうか、(中略)そう云うことを考えるのは小説家の空想であって、もはや今日になってしまった以上、もう一度逆戻りをしてやり直す訳に行かないことは分りきっている。だから私の云うことは、今更不可能事を願い、愚痴をこぼすのに過ぎないのであるが、(以下略)
ここで谷崎の「強烈なまでの『西洋礼讃』の反動」について論じることにはあまり意味がない気がする。もっとも重要なのは、「陰翳礼讃」において列挙されている「陰翳」の数々はすべて「小説家の空想」である、と谷崎自身が明言している点だ。「陰翳礼讃」に登場した「羊羹」は、谷崎が脳裡に描いた空想を具象化した作品なのである。本来の働きや役割を剥奪され、代わりに新たに価値づけされた事物ということで、このような作品をダダ・シュルレアリスム風に以後<オブジェ>と呼ぶことにしたい。
■ 架空の世界モデルの構築
<オブジェ>製作のための谷崎の空想は、「庇が作り出す深い廣い蔭の中へ全体の構造を取り込んでしまう」日本建築に言及する段に至って本領を発揮する。
われわれはよく京都や奈良の名刹を訪ねて、その寺の宝物と云われる軸物が、奥深い大書院の床の間にかかっているのを見せられるが、そう云う床の間は大概昼も薄暗いので、図柄などは見分けられない、ただ案内人の説明を聞きながら消えかかった墨色のあとを辿って多分立派な絵なのであろうと想像するばかりであるが、しかしそのぼやけた古画と暗い床の間との取り合わせが如何にもしっくりしていて、図柄の不鮮明などは聊かも問題でないばかりか、却ってこのくらいな不鮮明さがちょうど適しているようにさえ感じる。つまりこの場合、その絵は覚束ない弱い光を受け留めるための一つの奥床しい「面」に過ぎないのであって、全く砂壁と同じ作用をしかしていないのである。
実際の姿かたちなど、もはや一切問題にされていないのだ。そこにはただ、自らの空想を投影できる「面」さえあれば事足りる。このように谷崎の言葉は、物事の実体を正確に描写しようとするのではなく、脳裡の空想で物事をこねくりまわし、次から次へとひたすら<オブジェ>化していく。その執拗な作業の果てに「陰翳礼讃」は成った。※2 谷崎は〈オブジェ〉としての「陰翳」を並べ立てることによって、「陰翳礼讃」という架空の世界モデルを提示することさえできればよかったのであって、ここには、掲揚あるいは参照されるものとしての「陰翳美」など一切語られていないのである。
この意味で、三島由紀夫が「世間の主張」に反して谷崎のことを「抽象主義の作家」と定義づけた次のような発言はとても興味深い。「谷崎さんの書きたかったことは(中略)非常に抽象的な、観念的な問題ですね。谷崎さんは、直接抽象的なものにバーッとはいっていくのですよ」(昭42・7に行われたドナルド・キーンと三島由紀夫の対談「谷崎文学について」より、『対談 日本の文学』(昭46、中央公論社)所収)。
前回のブログでも言及したとおり、谷崎文学の魅力は、マゾヒズムや古典美といったテーマに生々しく肉薄していくところにではなく、むしろその逆に、それらから言葉が遠く離れて抽象的な世界へと一人歩きしていくところにこそあるのだと思う。そして、未完の奇作「鮫人」の時点では活動写真への盲信に酔った行き先の定まらない千鳥足だったこの一人歩きは、十数年後の「陰翳礼讃」においては架空の世界モデル構築という明確な目的意識に支えられている。谷崎の<オブジェ>製作作業のひとつの到達点といえるだろう。※3
それにしても正直、日本古来の「陰翳美」のすばらしさに触れようとして読んでしまうと、「陰翳礼讃」はさっぱりおもしろくない。が、たとえばカルヴィーノの「見えない都市」でマルコ・ポーロが言葉巧みに描出してみせた奇妙な都市の輪郭と同じように、まったく新しい謎の世界モデルの素描として谷崎の「陰翳」をあらためて捉え直してみると、めっぽうおもしろい。だから「陰翳礼讃」を読む時には、マルコ・ポーロの報告を聞くフビライ汗になったような気持ちで、「ほう、どれどれ」とちょっと偉そうにかつ無邪気に本を開くのがお勧めである。
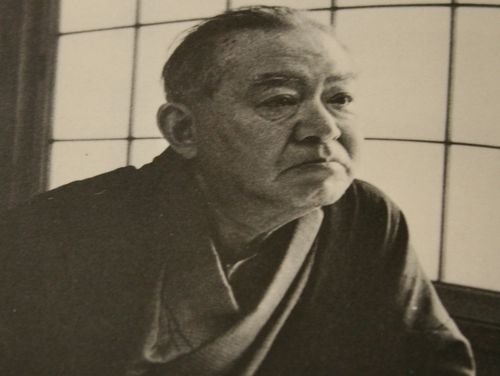


コメントを残す